|
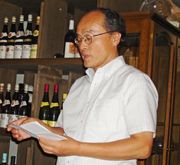
▲武井哲夫社長(武井工芸店)

▲小林玲子副会長(長野郷土史研究会)
|
|
長野郷土史研究会の小林玲子副会長に「地獄極楽の絵解きと善光寺」という演題でお話ししていただきました。
絵解きは中世から行われていました。普通はお寺の方が行うことが多く、長野ではかるかや山の絵解きが有名です。善光寺の善光寺聖は人数も多く、全国を回り、教えを広めていたようです。背中に厨子を背負って行き、厨子の扉を開くとご本尊が現れます。交通の便が良くない時代ですから出開帳の意味もありました。演じられた善光寺縁起は各地に残っています。今でも数多い善光寺講が作られ、維持されていたわけです。
本日の絵解きは「熊野勧進授戒曼荼羅」をやらせていただきますが、これは熊野比丘尼が行っていたものです。熊野神社には熊野聖の他に熊野比丘尼も多くいたようです。善光寺も女性に対し開かれていた数少ないお寺です。そのため熊野神社と善光寺はつながりが多くあります。今は元善町にある熊野神社と諏訪社も明治の神仏分離令までは善光寺に境内にありました。また東横田公民館で熊野勧進授戒曼荼羅が見つかっています。県内で見つかったことは関係者にとっては大発見です。熊野比丘尼が善光寺との縁で長野県内を回っていたことの証明になります。
熊野比丘尼は各地を回りながら、お札やなぎの葉を買ってもらって、勧進をしていました。主に女性を対象にやったようです。七五調の口上で絵解きをしていたようです。先に鳥の羽をつけた羽差しで絵中の場面を指しながら物語を語り、ひしゃくを使って勧進をしていました。それでは本日の絵解きをさせていただきます。
|